 |
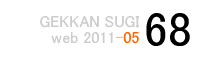 |
|
|||||||||||||||
| 私は吉野の杉山に魅せられ、素材を求め、長年足を運んできました。 製樽職人を目指した当初、吉野方言で杉山のことを「伊丹味山」、樽丸のことを「伊丹味」、樽丸師のことを「イタミ職」と呼ばれていることを知り、吉野の杉山への想いがますますつのりました。 |
|||||||||||||||
| 吉野で育てられた杉は口径が正円に近く、年輪が緻密であり、その上根元と末の太さが余り変わらずまっすぐに伸びているのが特徴で、かつ計画的に生産されてきたものです。このうち60年生から120年生のものが桶榑・樽丸として使われ、それ以下のものが建築材になります。 | |||||||||||||||
| さて皆さん、樽と桶の違いを御存知ですか? 樽は水や酒などを入れて貯蔵・運搬に使うもので、蓋が付いています。 桶も容器ですが道具としての使用が主なため、蓋はありません。 大まかに区別するとこんなところでしょう。 |
|||||||||||||||
 |
|||||||||||||||
| 樽。甲付(赤味と白太が半分半分の材料)を使用。 | |||||||||||||||
 |
|||||||||||||||
| 桶。こちらも甲付(赤味と白太が半分半分の材料)を使用。 | |||||||||||||||
| 樽は尺8・尺5・尺1と規格が決まっていて、樽材については吉野の山であらかじめ規格の板に加工されます。酒が漏らないよう板目が使われ、これを「樽丸」と呼びます。板目取りとは年輪にそった割り方で、年輪が木の芯に向かって曲がろうとする性質を利用し、これを蓋で固定することで本体と蓋が一体化し、容器としての樽が出来上がります。 | |||||||||||||||
また、樽は本来輸送用の容器として作られたとみて差し支えないと思います。 |
|||||||||||||||
昔の酒造り道具と、樽・桶を作る道具、樽丸を作る道具、またそれらから生まれ出た製品を見ていると、酒造りを支えていたのは「木の文化」だと痛感します。道具を使う側にも作る側にも、木の性質を良く知った上での独特な工夫が見られるからです。 |
|||||||||||||||
| 今、木についての知恵を持ち、道具を使いこなせる職人が刻々と姿を消しています。先人の知恵と技術にふれるにつけ、木の文化を後世に残し、日本の文化の一翼を担いたいと痛感しています。 | |||||||||||||||
| ●<たなか・けいいち> 兵庫県西宮市の樽商(株式会社田中製樽工業所)代表取締役。 和樽の文化を伝える灘五郷の樽職人。 |
|||||||||||||||
Copyright(C)
2005 GEKKAN SUGI all rights reserved |
|||