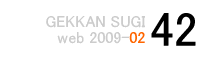|
連載 |
|
| |
スギダラな人々探訪/第36回 「再び、阿部直樹さんの巻」 |
文/
千代田健一 |
| |
杉を愛してやまない人びとを、日本各地に訪ねます。どんな杉好きが待ち受けているでしょう。 |
| |
|
|
 |
このコーナーは時々、イカれたスギダラ野郎の紹介コーナーになっていまして、今回もかなりイカれています。うそ。かなりイカしたことしてくれました。何と頼みもしないのに記事を投稿してくれたんです。
そのイカしたスギダラ野郎は、本誌20号のスギダラな人々探訪でご紹介した建築家でスギダラ病末期患者の阿部直樹さんです。前回ご紹介いただいたアパレルのショールームで飫肥杉を使い、毎日のように志村やに行っていた阿部さんはまたもや飫肥杉を使ったスギダラスポットを作ってくれました。
読んでいただければわかりますが、そのお鮨屋さんのオーナーさんまでグルにしてしまうような手口(スギダラトーク)には恐れ入りました。
是非、スギダラの集まりで行ってみようと思います。
このコーナーでは阿部さんのようなイカれたスギダラ野郎を紹介するだけでなく今後は今回のたけ江さんのように素敵なスギダラスポットの紹介もして行きたいと思っています。
毎回こんなんだったら、思いっきり楽だなー・・・来月も誰か投稿してくれないかなー・・・(ち) |
| |
|
| |
● |
| |
|
| |
「宮崎産の木材で作った江戸前鮨店で考えたこと」 |
文/写真 阿部直樹 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
チヨダラさん連載「スギダラな人々探訪/第19回」で念願のスギダラ・デビューを果たし、
海杉さん連載「スギで仕掛ける/第2回」で「スギダラ病末期症状の域」と診断された阿部と申します。
2006年から必ず毎年1物件は宮崎産の木材を使う設計を行ってきました。
その3例目で、昨年10月末に開店した江戸前鮨店の内装設計をご紹介致します。 |
| |
|
| |
近年の鮨店では鮨ネタの産地を謳うことはごく普通のことになっています。
それは食材の素性や産地に思いを馳せること、言い換えるとその物語を楽しんでもらうということです。
店舗そのものについても同じことがいえます。内装や器といった室礼(しつらい)において、
その材料や産地に思いを馳せ、物語を楽しむことが出来るわけです。
例えば木曽ヒノキは鮨タネでいうところの大間のマグロのようなもので、最高級の材料です。
このヒノキと同じモノがあの伊勢神宮にもあるかも、なんて考えると気分が盛り上がるわけですね。
しかし、若い施主の独立開店となれば予算に限りがあります。
銀座の高級鮨店のように木曽ヒノキなんて使えない−でも材料には何か物語がほしい−ということで、またしても(というかゴリ押しで)宮崎の材料を使うことを企てたのです。
建具や家具を含めた木部仕上のすべてを宮崎産飫肥杉、カウンターの材料は都城産銀杏(いちょう)、
これらの材料を使い設計することを主旨として、施主へ提案することにしました。 |
| |
|
| |
[ 材料見学 ] |
| |
 |
|
 |
| |
都城の原木市場 材木の量に圧倒されます |
|
この銀杏の樹齢はいったい何年なんでしょうか? |
| |
 |
|
 |
| |
銀杏の無垢材でお世話になった綾町の綾工芸さんの工場 |
|
綾工芸さんの敷地 無造作に置かれている宝の山 |
| |
 |
|
 |
| |
見学に伺った小林市のきりしま木材さんの工場 |
|
トロッコに載せた巨木をこのノコ歯でバッサリ |
| |

|
|

|
| |
切出した材木はこうして自然に乾燥させます |
|
この厚さ!見ているだけでヨダレが出てきます |
| |
|
 |
施主への説明とそのやり取りはこんな感じでした。
「宮崎の杉は生産量が日本一です。いい材料が安く手に入ります。ヒノキではなく銀杏のカウンターを持っている鮨屋なんか東京にはほとんどありません。最高級ではないけれど物語のある材料を使いながら、予算の範囲内で設計しますので、そんな材料の物語を楽しみませんか?」
すると施主から意外な答えが返ってきました。
「大間のマグロは素晴らしい魚ではあるけど、高級すぎて私は興味がありません。それほど有名ではない産地の魚でも、旬の時期は漁獲量が増え、いい魚が安く手に入ります。そんな魚に自分の仕事を加えてお客様に提供したい。私の鮨に対する考え方と阿部さんの設計の考え方は同じですね。」
考えてもみなかった施主の反応に勇み立ち、私はすかさず施主の意見に乗っかりました。
「そうなんですよ、産地に愛着のある材料は使いたくなるんですよね。」
本音がうっかり口から出た自分に驚き冷や汗が出ましたが、その後の施主の言葉に救われました。
「産地を知っていたり生産者が分かっていたりすると、安心して楽しく買物が出来て気分がいいですね。産地直送の食材が売れるのは、そういう理由じゃないでしょうか。分かりました阿部さん、その宮崎の材料で、僕だけの店を作って下さい。」
さすが鮨職人、食材流通の意味に反応すると同時に、私の意図を超える理解を示してくれました。
そんな理解力のある施主に助けられ、川上木材株式会社の川上宰社長(37号参照)にお世話になり、「鮨たけ江」は無事竣工しました。 |
| |
|
| |
[ 工事風景 ] |
|
|
| |
 |
|
 |
| |
設備配管を設置して土間コンクリートを流し込む |
|
川上木材さんから届いた材料 頑丈に梱包されています |
| |
 |
|
 |
| |
大工工事開始 |
|
仕事のキレイな大工親方 天井の杉板を丁寧に施工中 |
| |
 |
|
 |
| |
鮨屋内装最大の難所 カウンターの留め加工 |
|
いちょうのカウンター完成 美しすぎる! |
| |
 |
|
 |
| |
柱や長押、廻縁の取り合い 飫肥杉の赤身が効いてます |
|
木工事終了 床仕上タイルの調子をみる |
| |
|
| |
設計当初、宮崎産の材料を「ヒノキに対するアンチテーゼ」という意味でしか考えていませんでした。
また、そんな材料を上手に使って、立派な江戸前鮨店を設計してやる、と意気込んでいました。
しかし、「産地直送は楽しく気分がいい」という鮨職人の本質的な意見の前では、
私の底の浅いアンチテーゼなんて何の意味もなかったのでした。 |
| |
また、私の設計における信条は「材料にこだわらず頼らない設計」です。
そんなことを言いながら宮崎の材料にこだわるのは何故なのか?
2年前に初めて材料を買い付けに行った場所が宮崎でした。そしてその宮崎が産地として楽しく気分がよかったからにほかなりません。(私が他に産地や材料を知らないという根本的な理由もありますが) その楽しさや気分のよさの根源がスギダラにあることは、このサイトをご覧になっている皆さんであれば当然ご存知のことと思います。
「材料にこだわるつもりはないけど、産地は宮崎がいい」とは、聞き分けの悪い子供でさえ、こんなダダはコネません。こう言わしめる症状こそが海杉さんのいう「スギダラ病末期症状」だと思います。
設計者が産地に赴き材料と対面する喜びは、鮨職人が河岸に行くと心が躍ることによく似ています。
そんな産直設計の気分のよさが、私の設計を通じて少しでも多くの人へ伝えられたらと考えています。
それと、産地で行なう宴会の楽しさや気分のよさも同様に。(笑) |
| |
|
| |
宮崎への材料発注で、いつも私の担当していただいている、川上木材の福原さんという人がいます。
彼が出張で上京した際、「志村や(11号参照)」で酔いも手伝ってか私にこう言いました。
「阿部さんは何でぇ宮崎なんですかね?他の産地じゃあダメなんですか?わざ〜わざウチの材料使っていただけるだけで十分あり難いことなんですがぁ・・・」と宮崎弁特有のイントネーションで(笑)、
聞かれたことがありました。
ようやくその質問に答えられそうです。(映画「極道の妻たち」、かたせ梨乃の名セリフで)
|
| |
|
| |
「極道(産地)に惚れたんちがう。惚れたオトコ(宮崎)がたまたま極道(産地)だっただけの話や」、と。 |
| |
|
| |
[ 竣工写真 ] |
| |
 |
| |
共用階段から店舗を見る |
| |
 |
| |
正面から店舗外装を見る |
| |
 |
| |
出入口から厨房側を見る |
| |
 |
| |
厨房側から出入口を見る |
| |
 |
| |
飾棚を見る |
| |
 |
| |
付場を見る |
| |
|
| |
「鮨たけ江」概要 |
| |
店舗住所 |
東京都渋谷区神宮前2-31-7 地階 |
設計監理 |
阿部直樹建築設計事務所(担当:池田美子) |
施工監理 |
株式会社TNK企画 建築部(担当:冨成治之) |
店舗面積 |
9坪 |
座席人数 |
9席 |
器 |
中里太亀(陶芸家) |
暖簾 |
望月通陽(美術家) |
|
| |
|
| |
| * |
器や暖簾の製作依頼も作家の元へ施主と共に赴き発注した。
これも材料と同様に、施主に店の物語の中へ参加してもらうためである。
器は唐津の隆太窯、箸は豊後の竹箸を使うなど、宮崎産飫肥杉や都城産銀杏だけでなく、
九州に関わり合いがあるものが多い。
それは設計者が九州出身であることが最大の理由である。
この工事は株式会社TNK企画建築部の冨成氏なくして考えられなかった。
彼が施工を引受けてくれなければ、「鮨たけ江」は今でも開店していない。
この場を借りて厚く御礼申し上げます。
また、私に材料を見せるため、綾町・都城市・小林市の材木店や原木市場を、
丸一日掛けて案内していただいた川上社長には、感謝の言葉が見つからない。 |
|
| |
|
| |
|
| |
●<あべ・なおき>スギダラ会員No.556
阿部直樹建築設計事務所主宰 |
| |
|
| |
|
| |
● |
| |
|
| |
|
| |
●<ちよだ・けんいち>インハウス・プロダクトデザイナー
株式会社内田洋行 テクニカルデザインセンター所属。 日本全国スギダラケ倶楽部 本部広報宣伝部長 |
| |
|